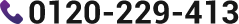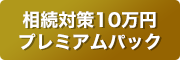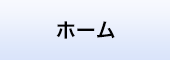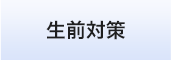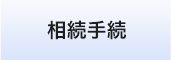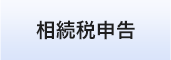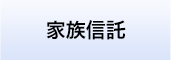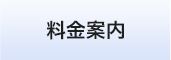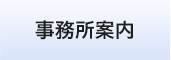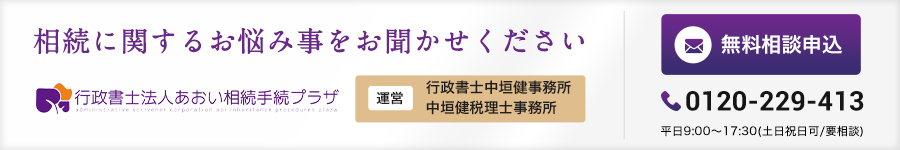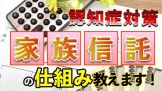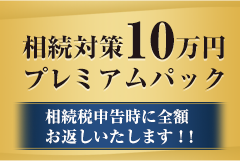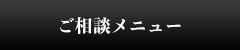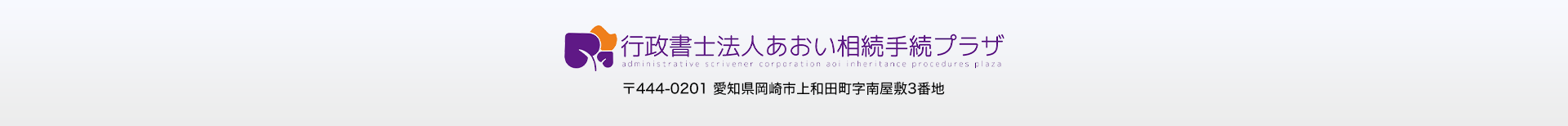もしご家族が認知症になったとき、「自宅を売却できない」「施設に入れない」「預金も自由に使えない」そんな状況になるかもしれないことをご存じでしょうか。
今回は、認知症によって起こる住まいやお金の凍結状態と、それを避けるためにどう備えておくべきかについてお話しします。
成年後見制度と家族信託、それぞれの仕組みや費用の違い、活用のポイントを比較しながら、認知症になる前にこそ考えておきたい具体的な対策を、実務経験豊富な専門家がわかりやすく解説しています。
ご家族の将来を守るために、早めの情報収集としてぜひご覧ください。
認知症が進行すると、法律的には契約ができない状態になってしまいます。
たとえば、ご実家を売却して老人ホームの入居資金に充てたいと思っても、認知症が進んだ後では売却の契約そのものが結べなくなるのです。
空き家になった家は、固定資産税や維持管理の負担がかかるだけでなく、ご近所からの苦情や損壊リスクなど、次第にトラブルへと発展していきます。
では、そうなってから対策を講じるとどうなるのでしょうか?
選択肢は「成年後見制度」ですが、この制度は財産の保全が目的であり、柔軟な資産活用や相続対策には向きません。
月3〜5万円前後の後見人報酬がかかり、10年間続けば600万円近くの負担になることも。しかも、家族が自由に預金を使えないことも少なくありません。
一方で、認知症になる前にできる対策として注目されているのが「家族信託」です。
家族信託では、あらかじめ契約を結ぶことで、生前の資産管理から相続後の分配までをスムーズに進めることができます。初期費用は30〜100万円程度ですが、将来的な自由度と安心感を得る手段としては非常に有効です。
どちらが正解ということではありませんが、何もしないまま時間が過ぎてしまうのが、最も大きなリスクとなります。
もし、ご家族の将来や資産管理に不安がある方は、ぜひ今のうちに選択肢を知っておいてください。
それが、ご本人にとっても、ご家族にとっても、後悔のない備えになるはずです。
たとえば、ご実家を売却して老人ホームの入居資金に充てたいと思っても、認知症が進んだ後では売却の契約そのものが結べなくなるのです。
空き家になった家は、固定資産税や維持管理の負担がかかるだけでなく、ご近所からの苦情や損壊リスクなど、次第にトラブルへと発展していきます。
では、そうなってから対策を講じるとどうなるのでしょうか?
選択肢は「成年後見制度」ですが、この制度は財産の保全が目的であり、柔軟な資産活用や相続対策には向きません。
月3〜5万円前後の後見人報酬がかかり、10年間続けば600万円近くの負担になることも。しかも、家族が自由に預金を使えないことも少なくありません。
一方で、認知症になる前にできる対策として注目されているのが「家族信託」です。
家族信託では、あらかじめ契約を結ぶことで、生前の資産管理から相続後の分配までをスムーズに進めることができます。初期費用は30〜100万円程度ですが、将来的な自由度と安心感を得る手段としては非常に有効です。
どちらが正解ということではありませんが、何もしないまま時間が過ぎてしまうのが、最も大きなリスクとなります。
もし、ご家族の将来や資産管理に不安がある方は、ぜひ今のうちに選択肢を知っておいてください。
それが、ご本人にとっても、ご家族にとっても、後悔のない備えになるはずです。