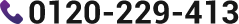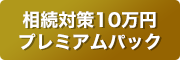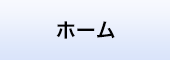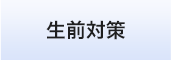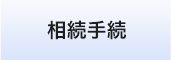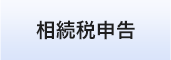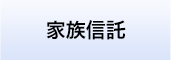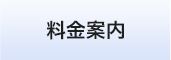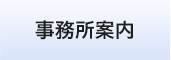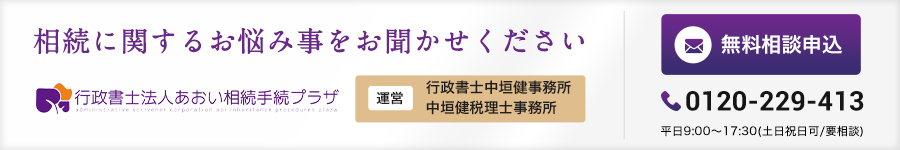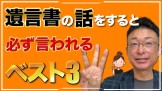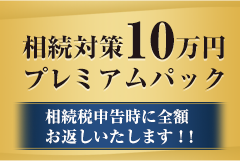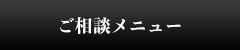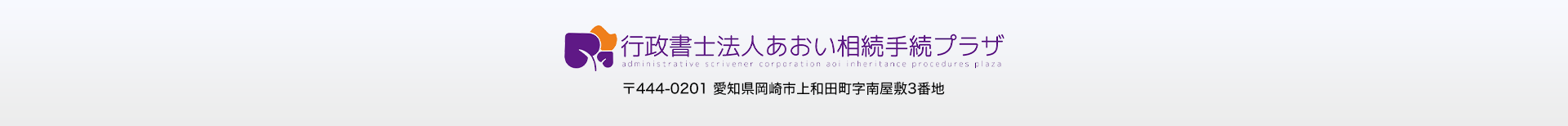「親が認知症になったら、預金って引き出せないんですか?」
こうした疑問をお持ちの方、実はとても多いです。
預金の管理は、認知症対策の中でも特に現実的な問題です。
たとえ家族であっても、判断能力を失った親の預金を自由に動かすことはできず、結果的に介護費用や施設入居費を立て替え続けることになるケースもあります。
今回の動画では、認知症が原因で預金が凍結されてしまう背景とその影響、そして「健康なうちにしておくべき備え」について、わかりやすくお話ししています。
認知症になると、ご本人に代わって契約や財産管理をすることが非常に難しくなります。
特に預金に関しては、金融機関側も慎重になっており、家族が窓口に同行しても引き出しが認められないというケースは珍しくありません。
また、相続時と違って、認知症による預金の凍結は長期化するのが特徴です。
平均で10年前後の介護期間が続く中、その間ずっとご家族が立て替えをするとなると、経済的な負担は相当なものになります。
さらに、認知症だけでなく、脳梗塞や意識障害などでも「法的な死」とみなされ、まとまった資金が必要なタイミングで動かせないというリスクがあることも、忘れてはいけません。
介護施設への入居一時金や、日常的な医療・介護費用は、年金収入だけでは到底まかなえないのが現実です。
だからこそ、元気なうちに、どのように預金を管理し、どのように資産を移しておくか、しっかり考えておく必要があります。
「うちはまだ大丈夫」と思っている今こそが、実は一番の対策チャンスです。 大切な資産を守り、将来の不安を減らすために、早めの準備を始めてみてはいかがでしょうか。
特に預金に関しては、金融機関側も慎重になっており、家族が窓口に同行しても引き出しが認められないというケースは珍しくありません。
また、相続時と違って、認知症による預金の凍結は長期化するのが特徴です。
平均で10年前後の介護期間が続く中、その間ずっとご家族が立て替えをするとなると、経済的な負担は相当なものになります。
さらに、認知症だけでなく、脳梗塞や意識障害などでも「法的な死」とみなされ、まとまった資金が必要なタイミングで動かせないというリスクがあることも、忘れてはいけません。
介護施設への入居一時金や、日常的な医療・介護費用は、年金収入だけでは到底まかなえないのが現実です。
だからこそ、元気なうちに、どのように預金を管理し、どのように資産を移しておくか、しっかり考えておく必要があります。
「うちはまだ大丈夫」と思っている今こそが、実は一番の対策チャンスです。 大切な資産を守り、将来の不安を減らすために、早めの準備を始めてみてはいかがでしょうか。